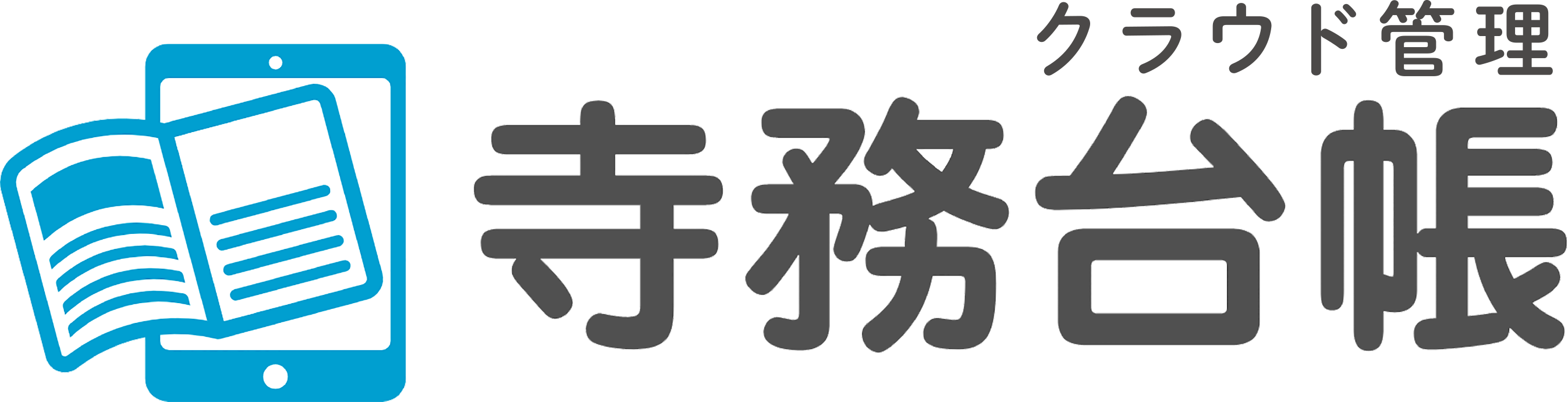導入事例(ご利用例)
檀家と寺の交流記録を残し、守っていくのは寺院の義務
蓮宝寺 (れんぽうじ)
浄土宗 東京都府中市
- ご利用期間
- 2年10ヶ月(2025年8月現在)
- ご利用プラン
- 基本プラン
- ご利用人数
- 2名(住職・奥様)
導入の決め手は「檀信徒カルテで未来に残せる檀信徒との関係性」
――檀信徒台帳や過去帳をデジタル化しようと思った理由、きっかけを教えてください。
前住職である父があまり事務作業に興味がなく、祖父母が残した記録も紙のままで過去帳も字が達筆というか特徴的で判読できないものもあり、母が「後で困るから、ちゃんと清書して残して」と話していましたがなかなか対応しませんでした。
宛名印刷も手書きのカードを機械に通すようなアナログな手間のかかる作業でした。小さなお寺なので約180件とはいえそれを自分が対応できる自信がなく、大学生の時からフロッピーディスクに入力していました。大学卒業後、企業勤めをしていましたが、顧客管理はあたりまえでした。お寺でも必要性を感じてEXCELにデータ化する作業は進めていました。
――『クラウド管理 寺務台帳』をどのように知りましたか?
(クラウド管理寺務台帳を運営するせいざん株式会社の取締役)池邊さんが私主催の研究会メンバーということもあって、開発当初から相談を受けていた。ただ池邊さんが「小川さんのところにはできているから必要ない」ということでなかなか誘ってくれなかった。(笑)

小川住職と池邊(クラウド管理寺務台帳責任者)
――『クラウド管理 寺務台帳』の導入の決め手は?
(出会った方や檀信徒と)仲良くなることをテーマにしているお寺なので、クラウド管理寺務台帳の「檀信徒との関係性を残していく」という開発目的と合致していたから。あと、妻にも協力してもらってEXCELでカルテのようにまとめてあった情報をDropboxで閲覧はできたが、外にいる時にスマホから編集ができなかったし、検索性も悪かった。法事が終わって、「ああ、なんか色々お話聞いたな」っていうのをパパパッと入力するのは不便を感じていた。疲れて帰ってきてパソコンを開いて入力することができなくて、記録しなきゃとおもってもできていなかったのも1つの理由。名簿だけではなく、色んな情報を記憶をちゃんと記録してけるようなのがいいなと思ったので、比較も特にせず導入を決めました。

クラウド管理寺務台帳スタッフのコメント
蓮宝寺は、創建から70年ほどの歴史を持ち、お墓を持たない「信徒寺」という特徴があります。そのため、檀家との関係性は「お墓」のつながり有りきではなく、寺院と人との交流が中心となります。それにも関わらず蓮宝寺を頼る信徒は増えています。
宗教離れや供養の縮小が嘆かれている時代ですが、小川住職は出会いをこつこつと大切にされ、過去10年で得た仏縁は施主名簿の数で見ると、倍近くになりました。EXCELも当初は寺務台帳の導入が不要なのでは?と感じるほど見たことがないくらい丁寧に作り込まれていました。葬儀社などの依頼により得た新たなご縁もよくお話を聞いて、できるだけ丁寧に対応されていることで、葬儀の再依頼や法要の依頼につながっています。
信徒一人ひとりの「生きた記録」を次世代に残せる体制づくりは、供養心や信仰心を育て、お墓がない寺院でも頼っていただける実例と言えます。
クラウド管理寺務台帳の導入後の変化とは?
――『クラウド管理 寺務台帳』の導入後、どんな風に利用していますか?
- 日々の業務への活用: 例えば法事。まず依頼を受けた時点でクラウド管理寺務台帳から入力。法事の前に、檀家情報を確認し、戒名や俗名、没年月日などを手元のメモに書く際に開いています。間違いがあっちゃいけないので。あとは故人様の人柄とかも記録してあれば確認しますね。葬儀なども同様です。事前に情報を確認しとくと、心の余裕ができています。
- コミュニケーションの質の向上: クラウド管理寺務台帳があればすぐに各家の次の法要がわかるので、法要後、お見送りをする際に「再来年がおじい様の何回忌ですね」といった声をかけるなど、檀家一人ひとりに寄り添った会話ができるようになりました。あとは、故人の中に100回忌を迎える方がいた場合は「今日の法要で一緒に100回忌のお勤めもしますね」などの提案もできるように。さすがに100回忌の故人は誰も知らないから、わざわざお集まりになるのが大変なのはわかるので、せっかくなら一緒に弔いましょうと言える。
- 記録の重要性: 過去の会話や故人の情報、家族構成を記録する。うちは枕経でお話を伺ったり、枕経ができなくてもできるだけお話を聞いて、諷誦文を作っているのでそれを画像保存する。各家の家族の様子やの故人を偲んだ様子を後世に残すことができるようになりました。その家の記録をちゃんと、責任を持って残すっていうのも、お寺の大事な役割と思っているので。
諷誦文や葬儀・法要の記録などもそのままクラウド管理寺務台帳に入れておけば、その方がどんな人生を送ったかっていうのが分かる。それこそね、私が死んで、誰が次を後継ぐか分からないですけど、いつかその方の50回忌になった時に、その方の諷誦文や記録を見れば、「こういうご生涯だったんですね」みたいな会話がお寺からできると思います。
それこそ、うちの祖父や父が作ってた過去帳は、戒名書いてるだけなので、どういう意味で付けたのかとか、どんな方だったのかが分からない。その点でやっぱりそういうのも残しておくことが大事だと思っています。
――『クラウド管理 寺務台帳』の導入後、檀信徒との交流で変わったことは?
「覚えておきたいな」「気をつけなければいけないな」と感じることは残すようにしています。
- 故人に関する情報: 戒名、俗名、没年月日だけでなく、亡くなった理由や生前の様子など、非常にデリケートな情報が含まれます。こうした情報を安易に尋ねたり、忘れて何度も同じことを聞いたりすることは、無意に遺族を傷つけてしまう可能性があるのでそうならないように記録して確認するようにしています。
- 家族構成の変化: 少子高齢化や家族の多様化が進む現代では、施主1人の住所や電話番号だけでなく、親族複数名の情報も重要です。その他にも婚姻・離婚、同性カップル、事実婚など、家族の形も変化しています。施主名簿と過去帳だけでは追いきれない情報を正確に記録することは、お寺と檀信徒との関係性を維持する上で大切だと感じています。
- 子ども・孫世代に関する情報: 何歳か、大学受験があるなど何気ないことも記録しておくようにしています。1年ぶりにお会いしたときにその話をしたいのに「何歳だっけ」「受験はおわったんだっけ?」など悩まずに話をして会話が続いていろいろとお話もしていただけるので仲良くなれるし、覚えておきたいことを記録してます。
前住職の父が亡くなった時は徐々に葬儀や法要の引き継ぎは受けていて、施主名簿も自分が整理していたのですごく困ったという記憶がない。ただ数年前に母がなくなった時は困ったことが多々あった。母の脳内メモがいかに大事かを感じる場面が多かったから。「あの人とあの人って、実際どういう関係なんだ」といったセンシティブなことが大事な情報なのに残っていないと相手を傷つけたり不快な思いをさせたりとヘマをすることになる。
できるだけ、相手を無為に傷つけたりしないようにクラウド管理寺務台帳に記録するようにしています。

クラウド管理寺務台帳スタッフのコメント
多くの寺院では、紙の台帳や住職・奥様の「脳内メモ」に頼っているのが実情です。しかし、代替わりや、住職・奥様の突然の逝去によって、その情報が引き継がれずに失われてしまうケースが少なくありません。クラウド管理寺務台帳にはどうしようもなくなってから困り果てて、ご相談に来られる住職や奥様の後悔の声もよくいただきます。
その点、クラウド管理寺務台帳では重要度別に記録できる場所を分けています。檀家との大切な記録が失われることは、お寺の歴史や信仰の継続を妨げることにもつながりかねない大きな損失であると小川住職は感じて、こまめに記録されておられます。また、クラウド管理寺務台帳では利用頻度からお困り事がないかをサポートできるように、ログイン状況を運営側で確認できる仕組みがあります。小川住職は常にログインしているため、運営スタッフから「大丈夫ですか?お困りごとがないですか?」と連絡をしたことがないほど日々ご利用くださっています。檀家との会話や故人に関するメモをこまめに入力したり参照することで、うろ覚えではない「確かな情報」に基づいたコミュニケーションが実現しています。これは、お寺の業務効率化だけでなく、檀家との関係性強化にも直結する重要な要素だと感じています。
――『クラウド管理 寺務台帳』の導入後、活用するコツは?
檀信徒との会話の中で、自分が受け止めたものが何だったのかっていうのは、その時話した人にしか分からないからこそ少しメモしておくだけで思い出すことができる。
ただ、会話の中で気合い入れすぎても駄目だと思います。
メモ取るぞと思って話聞いてたら、自然な話を聞けなくなっちゃうので良くないと思います。とりあえず意識せずに話を聞いて、それでも頭の中残ったものだけメモするというのが大事だと思っています。
お坊さんは話を聞く訓練を受けていないことがほとんどなのに、お坊さんは話を聞く訓練受けてるっていうふうに、誤解を持ってる一般の方って結構多い。つまり、話を聞いてほしい人が多いわけだから、自然に話を聞くことがまず基本。
あとは、LINEやSMSでの連絡やお手紙は住所がわかっているお家には細かに出すなどを積み重ねて、無意識の中でお寺のことを覚えといていただくことは意識しています。
檀信徒に興味を持って、話を聞いて会話を記録する。それが何より大事じゃないかと思います。

小川住職と池邊(クラウド管理寺務台帳責任者)
寺院が檀家情報を残し、守っていく重要性
――寺務台帳を導入するか悩んでいるお寺へメッセージをおねがいします。
「お寺にとって守るべきものは、ご本尊と建物、そして檀家さんの情報です。御本尊と建物のためには、相応の火災保険やセキュリティに費用をかけているご寺院がほとんどのことと思います。檀信徒の情報となると費用をかけて守る価値観を持たない方もいるようですが、企業組織では顧客管理への投資はあたりまえです。寺院の核である檀信徒の情報を大切に守っていくためにも、使い倒せば元は取れるシステムですのでランニングコストがかかることを理解した上で、前向きにご検討になってはいかがでしょうか。」
クラウド管理寺務台帳スタッフのコメント
月に数万円のコストを「高い」と感じるご寺院もおられます。しかし、火災保険やセキュリティ費用と同様に、檀家というお寺の「基盤」を守るための必要なコストとして考えてみると決して高くはないと弊社は考えています。また、大切な情報をお預かりして、費用をいただくシステムですので5年後、10年後の寺院経営を考える上での貴重な資産になるように日々開発を進めています。
取材に協力いただいた寺院
蓮宝寺
〒183-0004 東京都府中市紅葉丘2-41-3
浄土宗寺院。
戦後、現住職の祖父が東京都立多磨霊園の側に建立したとても小さなお寺です。
寺院墓地はなく、境内には大きな伽藍はありませんが、そのかわりに心がほっとやすらぐような、親しまれるお寺を目指されています。

今回お話を聞いた方

小川有閑(おがわゆうかん)さん
蓮宝寺 住職
第三世蓮宝寺住職
昭和52年生まれ
大学卒業→広告会社勤務→現在に至る。
平成28年3月7日に浄土宗から住職認証を得る。
住職のほか、大正大学地域構想研究所・BSR推進センター主幹研究員、浄土宗総合研究所研究スタッフなど研究分野でも活躍。
自死・自殺に向き合う僧侶の会正会員、一般社団法人自殺予防と自死遺族支援・調査研究研修センター理事など、自死予防・自死遺族支援の活動も。